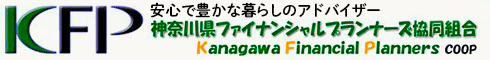2025年11月10日
令和7年度税制改正と年収の壁
令和7年12月1日施行の令和7年税制改正では所得に対する基礎控除等が見直され、いわゆる「年収の壁」が大幅に引き上げられました。これにより、就労意欲を阻害する制度的障壁の緩和が図られました。
具体的には、年収103万円の壁が160万円に引き上げられ、配偶者控除や住民税非課税の基準も変更されました。改正の背景には、少子高齢化による労働力不足と、パート・アルバイト層の就業調整による機会損失の是正があります。働き損を防ぎ、柔軟な就労を促すことが狙いです。
本コラムでは改正後の「年収の壁」について整理し見ていきます。
1.3つの「年収の壁」とは
「年収の壁」とは、一定の年収を超えると税負担や社会保険料が発生し、手取りが減る制度上の境界を指し、就労調整の要因となっているとされています。
主な壁は以下の通りです。
①税の壁:超えると本人に所得税乃至は住民税が課税されます。
②社会保険の壁:一定の条件下で健康保険・年金の加入義務が生じ、保険料負担が発生します。
③配偶者控除の壁:配偶者の所得が増えると控除額が減少します。
その他にも、「特定扶養控除の壁」「健康保険組合の扶養認定の壁」などがあります。
2.令和7年税制改正がもたらした「年収の壁」の変化
まず、税の壁では、給与所得控除が55万円から65万円、基礎控除が48万円から95万円に引き上げられ、所得税が発生する年収の上限が103万円から160万円に拡大されました。これにより、パート・アルバイトなどの短時間労働者が働き損を避けやすくなり、労働時間の調整をせずに就労できる環境が整いました。
次に、社会保障の壁では、106万円・130万円の壁に対して「支援強化パッケージ」が導入され、企業が保険料負担を軽減する仕組みや、従業員の社会保険加入を促す制度が整備されました。これにより、社会保険加入による手取り減少の不安が緩和され、安定的な就労継続が期待されます。
また、配偶者控除の壁では、控除対象となる配偶者の所得要件が48万円以下から58万円以下に緩和され、併せて給与所得控除も55万円以下から65万円以下に引き上げられたことで、年収123万円まで配偶者控除が適用可能となりました。これにより、配偶者の就労範囲が広がり、世帯全体の可処分所得の増加が見込まれます。
3.令和8年の確定申告での注意点
令和8年の確定申告では、令和7年税制改正により「基礎控除」「給与所得控除」「配偶者控除」などの適用条件が変更されているため、申告書の記載内容や控除額に注意が必要です。
以下に主な注意点をまとめます。
✔︎ 基礎控除額が一律48万円から所得額により最大95万円に引き上げられた他、令和7年及び令和8年には所得に応じて段階的に控除額が変動する「基礎控除の特例」が導入されました。
ただし、特例の一部は令和9年分以降は廃止予定のため、令和8年分での適用を忘れずに確認しましょう。
✔︎ 給与所得控除の見直しについて年末調整で控除されていない場合は、確定申告での申告が必要です。
✔︎ 改正に伴い、源泉徴収票の様式や記載項目が変更されているため、記載ミスや控除漏れの注意が必要です。
✔︎ 今回の改正は所得税のみが対象であり、所得税と住民税で控除額が異なるため、税額の差異に注意して申告書を作成しましょう。
4.過去に作成した「ライフプラン」の見直しも必要です。
令和7年税制改正により、所得控除や配偶者控除の上限が引き上げられたことで、手取収入(可処分所得)が増加する方が増えます。
また、年収の壁の緩和により就労調整の必要が減り、働き方の選択肢が広がります。
世帯収入の増加や社会保険加入の影響を踏まえ、老後資金や保障設計を柔軟に見直すことが重要です。
荒井 正巳 2025年11月10日